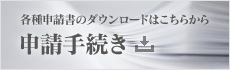洋学博覧漫筆
| ようあん |
| Vol.15 榕菴と植物学の出会い |
|
▲『植学啓原』 (津山洋学資料館所蔵) 宇田川榕菴が活躍したのは、杉田玄白らが『解体新書』を刊行してから50年余り過ぎたころです。すでに蘭学は医学にとどまらず学問のあらゆる分野へ広がり、榕菴も薬学や植物学へと研究を進めています。今回は、榕菴と当時は未知の学問だった植物学との出会いを紹介することにしましょう。 宇田川家の養子となった榕菴は、最初に医師の基礎教養となる漢方医学や本草学を学びました。本草学とは、植物や動物、鉱物の性質を調べて、薬としてどのような効能があるのかを明らかにする学問です。多くは植物でしたので、薬の本になる草、ということで本草学といわれていました。 幼いころから植物に興味のあった榕菴は、実際に山野に分け入って草花を調べたり、ときには玄真について薬草の研究会にも参加して、さらに植物への関心を深めていったのでした。 そんなとき、榕菴はショメールの『家庭百科事典』を読んでいて、西洋には日本とは全く違う植物の研究方法、「植物学」があることを知ります。 植物学では、本草学のように薬になる植物だけを取り上げるのではなく、植物すべてをその形状で分類し、顕微鏡で構造を調べて、植物も動物のように呼吸をしていることや受粉によって発生する仕組みなどが研究されていました。 これに驚いた榕菴は、さまざまな蘭書を調べ、植物学の概要を簡潔にまとめて『菩多尼訶経』(1822)として刊行します。 それからさらに12年の歳月をかけて、ついに天保5年(1834)に日本で初めての本格的植物学書『植学啓原』(全3巻)を刊行しました。この書には、美しい色刷りで植物の分解図や顕微鏡で拡大された細胞の図などが掲載されています。 序文を頼まれた同じ津山藩医の箕作阮甫も「これまで日本には本草学はあったが植物学はなかった。榕菴がアジアに初めて植物学を紹介した」と、惜しみない賛辞を送っています。 私たちが使っている「花粉」「繊維」などの植物の用語は、実は榕菴がオランダ語を翻訳したときに作った言葉です。榕菴の功績は今も身近なところに生きているのです。 |
| < 前号 | 記事一覧 | 次号 > |